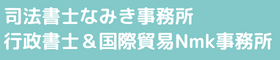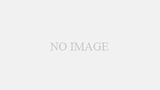このページでは、海外向けの第二種貨物利用運送事の「外航海運」と「国際航空」のより具体的な内容について紹介します。
第一種と第二種の違いなど、基本的な内容はこちらのページです。
各質問をタップしてください↓
お客様により異なりますが、一般的には申請の準備期間が2~3ヶ月、国土交通省の審査期間が3~4ヶ月です。
「利用運送事業」という名の通り、自社で船舶や飛行機を持たず、実運送事業者(船会社や航空会社など)と運送委託契約を締結して、船や飛行機で海外向けの運送を手配する事業が利用運送事業です。
この運送委託契約の対象は、実運送事業者(船会社・航空会社など)に加え、他の利用運送事業者(フォワーダーなど)も利用が可能です。
なお、許可申請の際には、これらの運送事業者との間の運送委託契約書を提出する必要があります。委託先となる運送事業者と契約ができない場合は、そもそも申請できませんのでご留意ください。
運送委託契約書は、準備段階では無くても大丈夫ですが、申請の最終段階では必ず提出する必要があります。
必ずしも世界中どこでも運送できるわけではありません。
前提として、1つ前の項目に記載した通り、許可取得にあたって、委託先となる運送事業者と契約を締結します。
例えば、既存のフォワーダーであるA社と運送委託契約を締結した場合…
A社はフォワーダーですので、このA社も独自に利用運送事業の許可を有しています。そして、A社の利用運送事業の許可には、出発地や到着地のエリアが定められているはずです。※
仮にA社が東京発アメリカ向けとして利用運送事業の許可を有している場合は、A社に委託する貴社も同じく、東京発アメリカ向けの範囲内でのみ許可取得が可能です。
つまり、委託先の利用運送事業の許可と同じ範囲内でのみ、許可取得が可能です。
※厳密には、許可書ではなく事業計画や集配事業計画でエリアが定められています。
利用運送事業とは別に、「貨物取次事業」という概念があります。
貨物利用運送事業とは、荷主と運送契約を締結して荷主に運送責任を負う事業を指します。自社で運送状(B/LやAWB)を発行する形です。
これに対し、「貨物取次事業」とは、荷主に運送責任を負わず、貨物運送の取次ぎのみを行う事業を指します。
つまり、自社で運送状を発行しない場合は、「貨物取次事業」にあたり、「貨物取次事業」は規制がないので、特段の許可は不要です。
当事務所では第二種貨物利用運送事業の許可取得の代行を積極的に行っております。第二種利用運送事業の「外航海運」または「国際航空」をご計画中のお客様、ぜひ当事務所にご用命くださいませ。